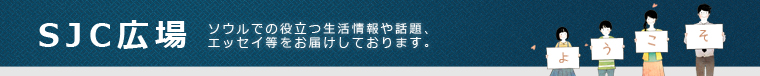
| 有名人エッセイ | 暮らしの話題 | SJC会員からの寄稿 | 韓国生活話 |
 14回目を迎える今年の「おまつり」は、「一緒につなごう 友情を未来へ」をテーマとして開催されました。
14回目を迎える今年の「おまつり」は、「一緒につなごう 友情を未来へ」をテーマとして開催されました。
1998年に金大中大統領と小渕総理大臣との間で署名された「21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ」宣言からちょうど20周年の記念すべき年でもあります。
また、この冬に開催された平昌冬季オリンピック・パラリンピックの成功を東京2020オリンピック・パラリンピックにつなげたいという気持ち。
加えて、昨年10月に「朝鮮通信使」がユネスコ世界遺産に登録されました。「朝鮮通信使」は「誠信交隣」の精神に基づく日韓文化交流の過去と未来を再評価できる貴重な文化遺産です。これらの精神を活かしたいからです。
おまつりの運営経過並びにプログラムのポイントは次のようです。
2 018平昌冬季オリンピック・パラリンピックは成功裏に終わりました。特に、スピードスケートの小平奈緒選手と李相花選手の最後の抱擁シーンは日韓両国のみならず世界中に感動を与えました。この感動をもう一度という気持ちから小平奈緒選手と李相花選手に出演をお願いしましたが、スケジュールが合わず、実現できませんでした。
しかし、次の3点にプログラムのポイントを置きました。
(1)日韓両国の伝統と現代の芸能プログラムを織り交ぜるとともに国技も交流させる。
(2)ユネスコ世界遺産登録を記念し、朝鮮通信使のパフォーマンスを再現する。
(3)平昌から東京までのメッセージを盛り込んだ「TOKYO2020」ブースを設置し平昌オリンピック・パラリンピックから東京2020オリンピック・パラリンピックへの友情のつながりをアピールする。
また、 広報活動にも力を注ぎ今年は 事前広報の一環として 「日韓交流おまつり Seoul2018 in Seoul記者懇談会」 を開催 し ました。 さらに 昨年同様 「 事前行」の開催やオンライベト、「 事前行」の開催やオンライベト、「 事前行」の開催やオンライベト、「Festival Wall 」の開設などを計画しまた。
「日韓広場」を設け、ストリートパフォーマンスのみならず両国の若者の交流を深める「ワークショップブス(交流の 場) 」も運営企画しました。
おまつり広報活動の一環として「おまつり」前夜の9月8日(土)にソウル市西大門区とともに,錦湖アートホール延世で事前行事を開催しました。西大門区とは2015年に「日韓国交正常化50周年」を迎えて延世路でパレードを実施したこと以来、今年も9月9日(日)の本行事に先立ち、事前行事を共同主催することになりました。
「おまつり」の本行事に出演する韓国の「楽音国楽団」と日本の「亀鶴屋」が出演しました。「楽音国楽団」は韓国の「南道アリラン」をはじめとする韓国の伝統曲に加え、日本の文部省唱歌「故郷」、東日本大震災のチャリティソング「花は咲く」などを演奏し、幅広い演出力を披露してくれました。
日本の伝統芸能の歌舞伎舞踊、立ち回りなどを身近で演出する「亀鶴屋」が色あでやかに「陰陽師」などを演じました。
日ごろ歌舞伎に触れることのない韓国の若者に歌舞伎の魅力を見せてくれました。

韓国の伝統曲など幅広い演出力を披露した
「楽音国楽団」

歌舞伎の魅力を韓国の若者に見せた
「亀鶴屋」
SJCハーモニー合唱団による歌声、祝賀メッセージ映像上映で式前行事が行われ開幕、オープニング公演は例年通りソウル市少年少女合唱団とソウル日本人学校によるハーモニーでスタートしました。その様子はまさに「一緒につなごう 友情を未来へ」のテーマそのものでした。
朴三求・韓国側実行委員長(錦湖アシアナグループ会長)並びに佐々木幹夫・日本側実行委員長(三菱商事特別顧問)の挨拶・開会宣言が声高らかに行われ、来賓の挨拶の後、長嶺安政・在大韓民国日本国大使が祝辞を述べられ、「おまつり」を手始めとして「21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ」宣言20周年記念の公式行事の幕が切って落とされました。
公式行事の最後は朝鮮王朝から派遣される外交使節「朝鮮通信使」に日本への国書を伝達する様子、また、その後日本に向けて出発する様子のパーフォーマンスが威風堂々と再現され、当時の様子をよみがえらせてくれました。国書には「相互理解を深め、平和と繁栄の道を歩んでいこう」と書かれていました。

ソウル市少年少女合唱団とソウル日本人学校のオープニング公演

国書を持って出発する朝鮮通信使の威風堂々な様子を再現
今昔を組み合わせての演出を試みました。日本からの新しい演出は①「社会的意義のあるものへ」という信念で東大のサークルから出発したという和太鼓グループ「彩」は和太鼓を通じてたくさんの人々に元気を届けたいという気持ちで演 奏。続いての②津軽三味線、尺八、箏、太鼓の新和楽器集合体の「WASABI」は和楽器だけの音楽で和の格好良さを追求し、若い人たちに伝えたいと力強く演奏し会場に活気を与えました。旧い伝統芸能は➂阿波国(徳島県)を発祥とする盆踊りで,400年の歴史を持ち日本三大盆踊りの一つの「徳島阿波踊り」。女性のしなやかな踊りと男性のダイナミックの踊りに会場は沸きだちました。➃日本の伝統芸能の歌舞伎舞踊や立ち回りなどを身近で演出する「亀鶴屋」の演出に会場はうっとり静まり返りました。
韓国からは①「ハンウルリム芸術団」が出演しました。キム・ドクス芸術監督を中心にサムルノリという韓国固有の打楽器公演と講習を世界的に広めている民間芸術団として活動しています。今年も胸を響くパワフルな演奏を会場から舞台へ移動しながら披露しました。また、②「コレヤ」は 3 人の韓国伝統音楽演奏者とヴォーカリスト、ギタリスト、ワールドパーカッショニストが全世界の様々な伝統音楽とポピュラー音楽を融合させた新しいスタイルの韓国音楽を表現する舞台を見せてくれました。

胸を響くパワフルな公演を行った
「ハンウルリム芸術団」

多くの人々に元気を届けるため、和太鼓を演奏する「彩」
まず、「楽音国楽団」が事前行事に演奏したと同じように韓国の「南道アリラン」をはじめとする韓国の伝統曲に加え、日本の文部省唱歌「故郷」、東日本大震災のチャリティソング「花は咲く」などを演奏し会場を盛り上げました。
続いて、日本の「空手」と韓国の「テコンドー」の両国を代表する国技演技が披露されました。日本からは①帝京大学空手部の選手が日本の空手の型を披露しました。韓国からは②韓国国技院テコンドー演武団のダイナミックなアクションが披露されました。日本の空手が「静」だとすれば韓国のテコンドーは「動」という両国武道の違いも見ることができました。下関から来た「馬関奇兵隊」と釜山から来た「釜山奇兵隊」が友情のハーモニーの中、会場いっぱいに大きな旗を振りながら舞い踊りました。東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて日本中に民謡ガールズブームを巻き起こすために結成された女子チームの「民謡ガールズ」は民謡ばかりでなくダンスも取り入れて会場を沸かせました。トロットガールグループの元祖として活動中の「レディティー (Lady T)」の舞台が行われました。最後は今年も日韓コスプレー公演、自分一人で楽しむのではなく、舞台に立てば公演となり、観客も楽しめるコスプレはすっかりおまつりの名物になりました。

帝京大学空手部の選手が日本の空手の型を披露

韓国国技院テコンドー演武団のダイナミックなアクションに場内から大歓声が沸き起こった。

民謡ガールズブームを目指して結成された
「民謡ガールズ」

トロットガールグループの元祖として活動中の
「レディティー」
特別公演は若者に人気の J-POP, K-POP の出演になりました。日本からは2013年に結成された男子5人組の J-POP「Flow Back」。韓国からは今や人気絶頂の K-POP「MOMOLAND」。「MOMOLAND」の名前はミヒャエル・エン デの童話「モモ」になぞらえてつけられたようです。彼女らのパーフォーマンスによって、その名前の由来のように時間に追われている観客はひとつづつファンタジーを取り戻せたようです。
フィナーレ公演の前座は ①韓国の青紗燈篭と日本の提灯が厳かに会場を照らす中、②「徳島の阿波踊り」がにぎやかに盆踊りを舞い、続けて③「民謡ガールズ」が三味線と軽やかなダンスで会場を盛り上げ、④「馬関奇兵隊」と釜山から来 た「釜山奇兵隊」が会場いっぱいに大きな旗を振りながら舞い踊り、フィナーレの準備が整いました。会場中央の舞台で⑤SJC を中心としたメンバーが「よさこいアリラン」を舞いながら会場おりて、➅金徳洙監督が率いる「サムルノリハン ウルリム芸術団」がサムルノリの演奏及び踊りを会場いっぱいに繰り広げ、最後のフィナーレ公演に続けていきました
フィナーレ公演は「馬関奇兵隊」と「釜山奇兵隊」の振る旗が大きくなびく中、朴三求実行委員長夫妻、長嶺駐韓日本大使夫妻も加わり両国の老若男女が「よさこいアリラン」、「ハンウルリム芸術団 」の踊りを会場いっぱいに繰り広げ、今年もまた、ビビンバ状態となり、興奮の渦に巻き込まれました。 交流の歓喜は会場いっぱいに響き、あたかも桜花と無窮花が咲き競うように「一緒につなごう 友情を未来へ」の気持ちで踊り続けていました。

今や人気絶頂の K-POP グループ「MOMOLAND」

男子5人組の J-POP「Flow Back」


「よさこいアリラン」を踊る朴三求実行委員長と長嶺駐韓日本大使夫妻
会場に設けた「日韓広場」では各種ストリートパーフォーマンスが繰り広げられ、その都度、大歓声が上がっていました。「Festival Wall」は日韓交流おまつりの応援メッセージをはじめ、日韓オリンピック応援メッセージなど観覧客からの心温まるメッセージでいっぱいになりました。また、若者の交流を深める「ワークショップブース(交流の場)」では日本人と韓国人がそれぞれに韓服と着物とを交互に着て、写真を撮り合ったりして新たな出会いを楽しんでいました。 また、日本の祭りには欠かせない「金魚すくい」と「ヨーヨー釣り」は子供たちが列を作るほどの賑わいでした。単なる「おまつり」のパフォーマンスばかりでなく、企業の展示会も含め地方自治体交流、青少年交流、飲食物、衣服、遊戯具などの各種文化交流が幅広く展開されていました。

日韓広場の「Festival Wall」で応援メッセージを書く人々

日本の祭りには欠かせない「金魚すくい」を楽しむ子供たち
「おまつり」には若者を中心に昨年と同様約6万余の人々が集まりました。今年は、同日に北朝鮮の建国70周年記念行事が開催されたり、MERS(中東呼吸器症候群)対応臨時会議が招集され、国務総理や外交部長官など政府の幹部の参加はありませんでした。しかし、金大中大統領と小渕総理大臣との間で署名された「21世紀に向けた新たな日韓パートナーシ ップ」宣言20周年記念年の公式行事の口火を切ったことに大きな意味を感じています。
今年の「おまつり」の成功主要因は以下のようなことが考えられます。
• 公演の量より質に重点を置いた。特に、ユネスコ世界遺産登録を記念して朝鮮通信使のパフォーマンスを再現したこと。
• 今年はより広報活動にも力を注ぎ、「日韓交流おまつり 2018 in Seoul 記者懇談会」の開催を始め、「事前行事」や「オンラインイベント」、「Festival Wall」の開設などを実施したこと。
• 例年通り「日韓広場」で各種ストリート・パフォーマンスを繰り広げ、日本人と韓国の若者の新たな出会いの場「交流の場」を作ったこと。
• 地方自治体交流、青少年交流にくわえ、飲食物、衣服、遊戯具などの各種文化の体験コーナーに工夫を凝らしたこと。
• 厳しい経済環境の中でこのおまつりの意義を理解し、ご協力いただいた企業や個人が支えてくれていることは言うまでもないことです・・心より感謝申し上げます。
• この「おまつり」の事務局体制も確立して、協賛金集めをはじめ事務処理が昨年に比べてよくなっていること。
• この「おまつり」は単なる文化交流にとどまらず地方自治体交流、青少年交流、飲食物、遊戯などの各種文化交流を含む「複合文化交流」でなのです。よって、両国民がお互いの文化や歴史や生活風習などをさらに理解し合う工夫や、広報活動を活発にしなくてはなりません。
• 政治・外交問題とは一線を画す催しですが、両国間に長く漂う政治・外交問題に「友好親善」のヒントを与える催しにしなくてはなりません。
• 「おまつり」は両国の間にどんな悪天候があっても、常に進むべき方向を教えてくれる灯台の光のような「日韓友好の
シ ンボル」なのです。
• この「友好日韓のシンボル」を継続するためにこのところ減少傾向の協賛金をいかに増加させるか各企業様のご理解を賜り、両国市民、特に若者に「おまつり」の意義を伝承していくことが鍵であると考えています。
改めて、「おまつり」にご協賛、ご協力いただいた皆様に感謝するとともに、これからも引き続きご理解とご支援をお願い申し上げる次第です。
2018年8月23日(木)11時から在韓日本大使館公報文化院3階のニューセンチュリーホールで「日韓交流おまつり2018 in Seoul」記者懇談会」が行われました。
 行事は高杉暢也「日韓交流おまつり」の名誉委員長兼実行委員が日韓交流おまつりの歴史と足跡を紹介することから始まりました。 2005年の日韓国交正常化40周年を記念して「日韓友情年」が始まり、その最初の行事から市庁広場と清渓川広場を経て、COEX展示場に移動し、行事を進行する現在までの歴史を一目瞭然に整理しました。
行事は高杉暢也「日韓交流おまつり」の名誉委員長兼実行委員が日韓交流おまつりの歴史と足跡を紹介することから始まりました。 2005年の日韓国交正常化40周年を記念して「日韓友情年」が始まり、その最初の行事から市庁広場と清渓川広場を経て、COEX展示場に移動し、行事を進行する現在までの歴史を一目瞭然に整理しました。
今年の「日韓交流おまつり」公演の目玉があります。まさに「朝鮮通信使の再現パフォーマンス」ですが、「日韓交流おまつり」で、このようなパフォーマンスをするのは極めて重要な意味を持ちます。 朝鮮通信使が往来していた204年間、両国は政治、文化交流を活発にし、平和な時代を送ったのです。 日韓両国の友情の象徴である「日韓交流おまつり」行事に、これよりふさわしいものがあるでしょうか。
2017年10月31日、朝鮮通信使はユネスコ世界記録遺産に登録され、「日韓交流おまつり2018 in Seoul」で当時の雰囲気を少しでも感じることができるように再現します。 朝鮮通信使については、関連する本を監修した沈揆先(シム・ギュソン) 、「日韓交流おまつり」実行委員が紹介しました。
田中将志運営委員長からのプログラムの紹介が続きます。 今年は特に、日韓合作映画「大観覧車」日韓俳優の舞台挨拶と韓国のアイドル「MOMOLAND」公演として、さらに多彩で楽しい行事になるという説明もありました。記者団の質疑応答に4人の委員が心を込めて答えてくれました。 「より多くの人が、参加できる行事になってほしい」という記者団の願いに答え、これからはよりよい行事をさらに積極的に知らせるように努力するという答えで、記者懇談会を終えました。

